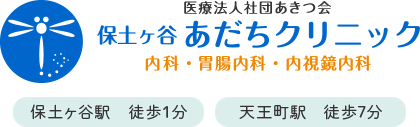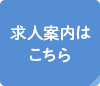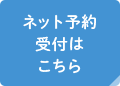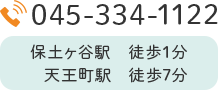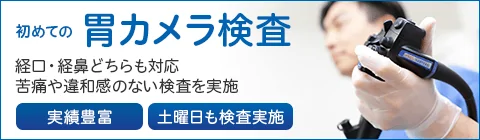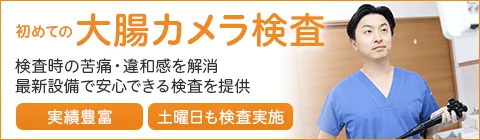保土ヶ谷区で内科クリニックをお探しの方へ
■保土ヶ谷区で内科クリニックをお探しの方へ
体調を崩された際にまずみなさんが相談先として思い浮かぶのが「内科」を標榜しているクリニックかと思います。発熱や咳、のどの痛み、倦怠感、腹痛、下痢、便秘、頭痛、吐き気などの症状は内科クリニックで幅広く対応することができます。また、生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症)や、睡眠障害、健康診断で異常を指摘された際、慢性的な体調不良の相談先としても内科は重要な役割を担っています。
当院も発熱外来から、一般内科外来、生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病など)、睡眠時無呼吸症候群、消化器外来、内視鏡検査、健康診断、予防接種など幅広く診療を提供しています。保土ヶ谷区で内科クリニックを探されている方がいらっしゃいましたらお気軽に当院までご相談してください。
■内科クリニックは何か違和感を感じた際の最初の相談窓口となります
内科は、特定の臓器に限らず、全身を総合的に診ていく診療科目となります。「どこにかかればいいかわからない症状」であっても、まず内科クリニックを受診することで、必要に応じて専門科への紹介や追加検査が可能となります。特に、複数の症状が併発している場合や、原因がはっきりとわからない場合には、内科クリニックにお越しいただければ総合的な視点で診療を提供することができます。
■横浜市保土ヶ谷区で内科クリニックを選ぶ際のポイント
内科クリニックも数多くあります。どこで受診するかで迷ったときは、以下のポイントを参考にしてみてください。
1.幅広い症状に対応しているか
風邪や咳、腹痛、下痢、胃腸炎などの急性疾患だけでなく、生活習慣病や慢性疾患、健診後のフォローアップまで幅広く対応しているクリニックは、かかりつけクリニックとして通いやすいです。HP上に幅広く診療を提供している内科クリニックを受診するようにしてください。
2.丁寧な説明と相談しやすさ
自身の症状や検査結果について、分かりやすく説明してくれるかどうかはとても重要です。「些細な症状であっても相談しやすい雰囲気」がある内科クリニックでは、早期受診・早期治療につながります。
3.検査体制が充実しているか
血液検査、尿検査、心電図、レントゲン、超音波検査、内視鏡検査などを実施しているかどうかは、診断の正確さにも直結します。検査体制が整っているクリニックを受診するようにしてください。
4.通いやすさ・アクセス
保土ヶ谷駅から近い、診療時間がライフスタイルに合っている、予約が取りやすいといった点も、継続的な通院には欠かせません。
5.土曜日も診療を実施しているか
平日は仕事や家事、育児等で忙しい方もいらっしゃるかと思います。そういった方でも安心していただけるように土曜日も診療を実施しているかは確認するようにしてください。
■こんな症状があれば内科クリニックまで
次のような症状がある場合は、早めに内科を受診しましょう。
・発熱、咳、のどの痛み
・息切れ、胸の痛み、動悸
・腹痛、下痢、便秘、吐き気、胸焼け、胃もたれ
・めまい、むくみ
・寝起き頭痛、日中の眠気
・健診で血圧・血糖・コレステロールを指摘された
・原因不明のだるさや体重変動
■保土ヶ谷区で内科クリニックをお探しの方へ
内科といえば、日常の体調管理から病気の早期発見までを支えている、身近で頼れる診療科かと思います。保土ヶ谷区で内科クリニックをお探しの方は、対応できる疾患・症状、説明の丁寧さ、検査体制、アクセス、土曜日の診療の実施も参考にしてみてください。気になる症状がある方は、些細なことでも構いませんので、我慢せず、お早めに内科クリニックへ相談するようにしてください。
肝臓数値で異常を指摘された方へ
〇肝臓の働きについて
肝臓は人が生きていくなかで様々な役割を担っている臓器でありますが、肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれる臓器であり、自覚症状を感じにくい特徴があります。肝臓の機能が下がっていくと様々な病気が発症してしまうため、健康診断などで肝臓の数値で異常を指摘された方、些細なことでも構いませんので何か気になる症状を感じる方はお気軽にご相談してください。
〇肝臓の数値について
肝臓の状態を示す指標として、以下に記載をしているような項目がよく確認されています。下記の項目で異常を指摘された方はお気軽に当院までご相談してください。
・AST(GOT)・ALT(GPT)
AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)とALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)は、肝臓の細胞の中にある酵素です。肝臓の細胞が破壊されることで血液中にASTやALTが流れ出てしまいます。肝臓の機能が低下してしまっている場合は、血液検査でASTやALTの数値が高くなります。
・γ-GTP
γ-GTPは胆管や肝臓の細胞膜にある酵素です。アルコール摂取や脂肪肝が発症すると、γ-GTPの数値が上昇していきます。
・ALP
ALPは胆汁の流れに関係している酵素です。胆管に何か問題が生じると数値が高くなります。胆石で胆汁の通りが悪くなるとALPの数値は上昇します。胆管炎や胆管がんなどの胆管で生じる疾患でもALPは高くなります。
・ビリルビン
ビリルビンは赤血球が壊れたときにできる老廃物となります。ビリルビンは肝臓で処理されて胆汁として排出されます。肝臓でうまくビリルビンが処理できないと血液中にビリルビンが増え、黄疸(皮膚や白目が黄色くなること)が生じます。
・アルブミン
肝臓は体に必要なたんぱく質を作る役割があります。アルブミンは血液中にあるタンパク質であり、体内の水分を保ち、栄養素を全身に運んでくれます。肝臓の合成能力が低下してしまうとアルブミンは低下していき、むくみや腹水の原因となっていきます。
〇肝臓機能障害が生じる原因
肝臓の数値が高くなっていく原因は下記にあるように様々です。
- ◆生活習慣によるもの
- アルコールの過剰摂取
- 高カロリー食や肥満体型
- ◆ウイルス感染
- B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス
- ◆自己免疫や代謝異常
- 自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎など
- ◆胆管異常
- 胆管結石、胆のう結石など
- ◆悪性腫瘍
- 肝臓がん、胆管がん、胆のうがん、すい臓がんなど
- ◆薬やサプリメント
- 一部の薬剤の副作用
- 健康食品、サプリメント
〇肝臓障害で生じる症状
肝臓は自己再生能力があり、発症初期の段階では自覚症状を感じることはありません。ただ、病状が進んでいくと下記のような症状を引き起こします。
- 倦怠感、疲れやすさ(疲れが取れない)
- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)
- 腹部膨満感
- むくみ
- 意識障害(肝性脳症)
上記のような症状が慢性的に続いていくと肝硬変や肝がんなどの病気の発症リスクが高まります。些細な症状でも構いませんので何か違和感を感じる際は、何かおかしいと感じた際はお気軽に当院までご相談してください。
〇肝臓の検査項目について
肝臓の数値で異常が見つかった場合、必要に応じて以下のような検査を行っていきます。
- ◆採血検査
- ◆腹部超音波検査(腹部エコー検査)
- ◆CT検査(当院ではCT検査ができないため、近隣の医療機関と連携しております)
上記のような検査を実施し、肝臓機能が低下している原因を調べ、治療方針を決定していきます。
〇肝機能障害の治療と生活習慣の改善
肝臓機能が低下している場合は原因に応じて治療方針が異なります。
- ・アルコール性:禁酒が基本
- ・脂肪肝:減量、食事療法、運動療法
- ・ウイルス性:抗ウイルス薬による治療
- ・薬剤性:原因薬の中止・変更
- ・自己免疫性:免疫抑制剤による治療
- ・胆管異常:内視鏡による治療
- ・悪性腫瘍:外科手術など
また、肝臓機能が低下している際の治療で共通して大切なことは、普段の生活習慣の改善となります。肝臓機能で異常を指摘された方は以下の項目を意識してください。
- ・バランスの良い食事内容を意識する(脂肪や糖質の摂りすぎを控える)
- ・1日3食バランス良い食事内容を意識する
- ・適度な運動をする(定期的な有酸素運動を実施する)
- ・禁酒・禁煙をする
- ・規則正しい生活を送る
〇まとめ
肝臓は発症初期には自覚症状を感じることなく、健康診断などの採血検査で異常を指摘されて初めて肝臓病が発見されるケースがほとんどとなります。どんな病気でもそうですが、早期発見・早期治療が大切です。健康診断で肝臓の数値で異常を指摘された場合は、自覚症状がなかったとしてもお早めに当院までご相談ください。
大腸にとって消化が良い食べ物とは?
消化の良い食べ物とは?
消化の良い食べ物とは、胃腸に負担をかけずにスムーズに吸収・排泄される食品を指します。大腸にとって良い食べ物の条件は以下の3つです。
- ・腸内環境を整えるもの(善玉菌を増やす)
- ・便通をスムーズにするもの(適度な水分と食物繊維)
- ・消化・吸収を妨げないもの(脂質・刺激物を控える)
大腸の健康を保つためには、「やさしく、出やすく、育てる食事」がポイントになります。
大腸を整える基本原則
食物繊維のバランスを意識
食物繊維は便通改善に欠かせませんが、摂りすぎるとガスや腹部膨満感の原因にもなります。大腸に優しい摂り方は、「水溶性」と「不溶性」をバランスよく摂ることです。
- 水溶性食物繊維(便をやわらかくし腸内環境を整える)
→ オートミール、納豆、海藻、オクラ、山芋、アボカド - 不溶性食物繊維(腸を刺激して排便を促す)
→ ごぼう、きのこ、豆類、玄米、ブロッコリー
バランスとしては、水溶性:不溶性=1:2程度が理想です。
大腸にとって「消化の良い食べ物」とは
以下の食材は、胃腸に負担をかけず、かつ大腸を整えるのに役立ちます。
◎ 主食
白米、うどん、おかゆ、やわらかいパン(全粒粉よりも消化が良い)
オートミール(やわらかく煮ることで腸に優しく整腸作用もある)
◎ タンパク質
鶏むね肉・ささみ・白身魚・豆腐・卵(半熟程度)
脂の少ない良質なたんぱく源を中心に摂ることで、消化を助けます。
◎ 野菜・果物
にんじん、かぼちゃ、ほうれん草、じゃがいもなどの加熱野菜
バナナ、りんご(すりおろし)、桃などのやわらかい果物
生野菜よりも温野菜にすることで繊維が柔らかくなり、消化がスムーズになります。
◎ 発酵食品
ヨーグルト、納豆、味噌、甘酒、ぬか漬け
腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌の繁殖を抑える働きがあります。
特にヨーグルトは、乳酸菌の種類を変えながら継続摂取するのが効果的です。
◎ 飲み物
白湯、麦茶、ルイボスティー、具のない味噌汁
カフェインやアルコールは腸を刺激するため控えめに。
大腸に負担をかけやすい食べ物
大腸の健康を守るためには、「何を食べるか」だけでなく「何を控えるか」も重要です。
- ・脂っこい食事(揚げ物・バター・生クリーム):消化に時間がかかる
- ・刺激物(唐辛子・カフェイン・アルコール):腸粘膜を刺激し、下痢や腹痛を招く
- ・人工甘味料を含む食品:腸内細菌のバランスを崩す
- ・冷たい飲み物や食べ物:腸の血流を悪化させ、蠕動運動が低下
これらを控えめにすることで、腸の働きが安定しやすくなります。
調理法も大切 ―「やわらかく、温かく、シンプルに」
同じ食材でも調理法次第で腸への負担が大きく変わります。
- ・煮る・蒸す・茹でる → 油を使わず柔らかくなるので消化が良い
- ・焼く・揚げる → 油分や焦げが腸に刺激を与えるため控えめに
- ・温度管理 → 冷たい食事は腸の動きを鈍らせるため、温かい状態で摂るのが理想
特に便秘気味の方は、「温かくて柔らかい食事」を意識することで腸が動きやすくなります。
大腸の働きを助ける食べ方
「大腸にとって消化の良い食べ物」を選んでも、食べ方が悪いと効果が半減します。
- ・よく噛む(1口30回):唾液の消化酵素が働き、胃腸の負担を減らす
- ・規則正しい食事時間:腸のリズムを整え、排便サイクルを安定化
- ・腹八分目を心がける:食べ過ぎは消化不良・ガスの原因
- ・夜遅くの食事を避ける:就寝中は腸の動きが鈍く、便秘や膨満感の原因に
消化に良い食事例
【朝食例】
- おかゆ+具なし味噌汁+すりおろしりんご+白湯
→ 胃腸をやさしく温め、排便を促す理想的なスタート
【昼食例】
- うどん+温野菜+豆腐+ヨーグルト
→ タンパク質と発酵食品を組み合わせて腸内環境を整える
【夕食例】
- 白身魚の煮付け+かぼちゃの煮物+ほうれん草のおひたし+ご飯(やわらかめ)
→ 温かく消化の良い和食中心の献立
大腸と腸内細菌の関係
大腸には100兆個以上の腸内細菌が棲みついており、善玉菌・悪玉菌・日和見菌のバランスが健康の鍵を握ります。消化の良い食事は、善玉菌が働きやすい環境を作ることにもつながります。
- ・善玉菌を増やす食品:ヨーグルト、納豆、味噌、オリゴ糖
- ・善玉菌のエサとなる食品:水溶性食物繊維(海藻・大麦・果物など)
- ・腸内フローラを乱す要因:脂質過多、加工食品、抗生物質の乱用
腸内環境が整うと、便通改善だけでなく、免疫力の向上や肌荒れの改善、メンタルの安定にもつながります。
注意が必要な場合
次のような症状が続く場合は、単なる食事の問題ではなく、腸の病気の可能性もあります。
- ・長引く下痢・便秘
- ・血便や粘液便
- ・みぞおちや下腹部の痛み
- ・体重減少、食欲低下
潰瘍性大腸炎、クローン病、大腸ポリープ、大腸がんなど、専門的な治療が必要な病気のこともあります。症状が続くときは、早めに**消化器内科での検査(大腸カメラなど)**を受けましょう。
大腸にとって消化の良い食べ物とは?
「大腸にとって消化の良い食べ物とは?」という問いに対しての答えは、単に「柔らかいもの」ではなく、腸をいたわり、腸内環境を整える食べ物です。
|
ポイント |
内容 |
|
基本 |
温かく、柔らかく、油分少なめの調理法を選ぶ |
|
食材 |
白身魚、豆腐、やわらかい野菜、発酵食品 |
|
控えるもの |
揚げ物、アルコール、香辛料、冷たい飲み物 |
|
習慣 |
よく噛む・規則的に食べる・腹八分目 |
腸は「第二の脳」と呼ばれるほど、心身の健康に深く関係しています。大腸にやさしい食事を心がけることは、便通を整えるだけでなく、全身の健康維持にもつながります。日々の食卓を少し工夫するだけで、腸は確実に変わっていきます。今日からぜひ、「腸が喜ぶ食事」を意識してみてください。
いびきの原因と健康面への影響について内科医が詳しく解説します!
いびきについて
いびきは、睡眠中に空気の通り道である気道が狭くなり、空気の流れが妨げられることで発生する音のことを言います。
いびきが生じてしまう原因としては、何かしらの原因によって咽頭(のど)が狭くなって、空気が通る際にのどが振動して音がでることです。特に眠っているとのどを支えている筋肉が緩みますので、余計に咽頭が狭くなってしまいます。
いびきのセルフチェック
いびきは無意識にかいている状態です。いびきをかいていることを自覚することは難しいですが、下記のようなセルフチェック項目を参考にしていただければと思います。
・眠りが浅いと感じる(熟睡感を感じない)
・昼間に眠気を感じる
・眠くて注意力や集中力が続かない
・寝ても疲れが取れない(身体がだるく感じる)
・鼻がつまりやすい
・朝起きたときに口が乾いている
・寝起きに頭痛を感じる
・高血圧や糖尿病の治療を受けているがなかなか改善がしない
・肥満体型を指摘されている(BMIの数値が高い)
いびきの種類と特徴
いびきには、軽度のいびきから重度のいびきまでさまざまな種類があります。
-
単純性いびき
一般的ないびきのことです。気道が狭くなることで発生します。特に健康面に影響が生じていないなら、大きな問題ではないと思われますが、慢性的にいびきをかき続けていて睡眠の質が下がっていると将来的に病気の発症リスクが高まります。単純性いびきの原因としては、肥満体型、アルコール摂取、喫煙、鼻詰まりなどがあげられます。
-
閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)に伴ういびき
睡眠中に気道が完全に閉塞することで生じます。一時的に呼吸が停止することでいびきが発生してしまいます。閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)の原因としては、肥満体型、扁桃肥大、下顎の後退などがあげられます。
-
中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSA)に伴ういびき
脳の呼吸中枢で異常が生じることで生じます。呼吸が不規則になってしまうことでいびきが発生します。上記の『OSA』とは異なり、気道の閉塞が原因でいびきをかいている訳ではなく、中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSA)の原因としては、心不全や脳卒中、薬物の影響などが原因となります。
-
上気道抵抗症候群(UARS)に伴ういびき
気道が完全に閉塞する訳ではないですが、気道の部分的に狭くなってしまうことで呼吸が困難となりいびきが生じます。口を開けて寝てしまうことで生じるいびきで、のどが渇いて夜に起きてしまうなどの睡眠の質が低下にも繋がってしまいます。また、日中の眠気や疲労感(寝ても疲れが取れない)を引き起こしてしまいます。上気道抵抗症候群(UARS)の原因としては、肥満体型、鼻詰まり、アレルギーなどがあげられます。
いびきの原因
いびきの原因は、上述しているように空気の通り道である上気道が狭くなってしまうことで生じます。いびきをかいてしまう原因には、疲労、肥満体型、鼻詰まり、アレルギー性鼻炎・慢性鼻炎などが原因としてあげられます。
・疲労
・肥満体型
・鼻詰まりやアレルギー
・アルコールや薬物の影響
・喫煙
・年齢
・性別
・下あごが後退している
・扁桃炎の炎症、扁桃腺肥大
・睡眠姿勢
いびきの影響とリスク
いびきは睡眠の質を低下させるだけでなく、日中の眠気や集中力の低下、高血圧、心疾患、糖尿病、脳梗塞などの様々な病気の発症リスクを高めてしまいます。また、いびきが原因でパートナーの睡眠にも影響を与えることがありますので、いびきを指摘された方はお気軽にご相談してください。
いびきによる健康面への影響
睡眠の質の低下
いびきをかくことは睡眠を断続的に中断させているということであり、深い睡眠が妨げられてしまっています。しっかりと睡眠時間を確保してもいびきをかいている場合、日中の眠気や疲労感が増加してしまいます。
高血圧の発症リスクアップ
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と高血圧は密接に関わっていると言われています。SASに伴ういびきが原因となり、血圧上昇を引き起こし、高血圧の発症リスクを高めてしまいます。
心血管疾患(CVD)の発症リスクアップ
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患の発症リスクが高まります。いびきをかき続けることで、心臓や血管にも大きな負担がかかってしまいます。
脳卒中の発症リスクアップ
睡眠中に気道が詰まってしまうと、息をこらえた状態となります。息をこらえる状態となる度に、数秒〜数十秒だけ血圧が急上昇してしまいます。また、頸動脈の動脈硬化が進行してしまうことにも繋がりますので、脳卒中の発症リスクが増加してしまいます。
糖尿病の発症リスクアップ
睡眠不足や断続的な睡眠はインスリン抵抗性を高めてしまうことに繋がります。そのため、睡眠の質が下がってしまうことで糖尿病の発症リスクが高まります。
精神的な健康リスクアップ
睡眠不足はうつ病や不安障害などの発症リスクを高めてしまいます。睡眠の質の低下が、精神的な健康面にも影響を及ぼしてしまいます。
いびきは放っておいても大丈夫!?
飲酒した時や、かぜを引いた時だけいびきをかいてしまうなら、大きな心配はいらないかと思いますが、慢性的にいびきが続いている場合は普段の生活にも影響を及ぼしてしまいます。
中等症以上の睡眠時無呼吸症候群の方では、日中の強い眠気のため交通事故の危険性が高まってしまったり、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の原因となったり、精神面の不調を招いてしまうことがあります。些細なことでも構いませんので、いびきについて指摘をされた方、なんとなく体調面で違和感を感じる方はお気軽にご相談ください。
腹痛の原因について詳しく解説!
そもそも腹痛って?
腹痛は誰しもが経験をしたことがある身近な症状かと思いますが、大学病院などの総合病院へ救急搬送される症状としては「胸痛」と並んで腹痛は非常に多くなっています。腹痛が発症する原因は非常に多岐にわたり、どういった原因で腹痛が発症しているか特定するのも難しい症状となります。腹痛はよくあるありふれた症状ですが、診断が難しい症状でもあります。
腹痛の種類とは?
腹痛には、緊急性の高い腹痛とそうでない腹痛の2種類に分類されます。それぞれで腹痛が発症する原因は異なりますので下記をご覧ください。
|
緊急性の低い腹痛 |
便秘、胃炎、食道炎、メンタル疾患など |
|
緊急性の高い腹痛 |
出血が生じる病変(胃潰瘍や胃がん、大腸がんなど) 腸に閉塞が生じる病変(イレウスなど) 虚血性病変(血栓症や塞栓症、など) |
緊急性の高い腹痛の場合は、外科的手術やカテーテル治療などの治療を受けていただく場合がありますが、ほとんどの場合は何かしらの自覚症状を感じます。普段と違う腹痛だなと思われる際は、早急に内視鏡検査を行っているクリニックmでご相談してください。内視鏡検査で腹痛の原因となっている病気の特定と適切な治療を受けるようにしてください。
緊急性の高い腹痛って?
腹痛が自然に軽快していくことがなく、継続して痛みを感じる場合は緊急性が高い腹痛であるケースが多いです。また、今までに経験したことがないくらいお腹が痛む場合も緊急性の高い腹痛に該当します。下記のような症状を伴う腹痛の場合は、迷わず総合病院の救急外来に相談をしてください。
・歩けない程にお腹が痛む
・歩くとお腹に痛みがひびく
・背中を丸めていないと痛くて辛い
上記のような場合は、腹膜という膜で炎症が生じている可能性が高いです。この場合は緊急入院になる可能性がありますので、お近くの総合病院の救急外来を受診するようにしてください。
腹痛が生じている原因が分からないことってあるの?
腹痛が生じる原因は非常に多岐にわたります。腹痛が発症している原因を特定しようと検査を実施しても分からない場合があります。その場合は、精神的なストレスが原因となっている可能性が考えられます。この場合は過敏性腸症候群や機能性ディスペプシアなどの病気が関係しています。
過敏性腸症候群は人間関係で悩むことがあったり、強いプレッシャーを感じるような場合に便秘や下痢、腹痛などの消化器症状が発症します。また、過敏性腸症候群は内視鏡検査(大腸カメラ)で検査を実施しても特に何も異常が確認できないのが特徴です。
女性によくある腹痛とは?
女性の方で腹痛が発症する原因は年齢で考えられる原因が異なります。閉経前の方の場合は子宮や卵巣の病気が原因となって腹痛を発症していることがあります。そのため、閉経前の方で腹痛症状でお困りの方は婦人科と消化器内科の両方の科を受診していただく必要があります。閉経後の方の場合は、消化器内科関連の病気が腹痛の発症に関わっている可能性が高いです。消化器内科を標榜しているクリニックを受診するようにしてください。
痛みに波があるときってどんな腹痛?
お腹の痛みを感じたり、痛みが自然と消失したりを繰り返す腹痛もあり様々です。痛みに波がある場合は、前述している緊急性の低い腹痛に該当されることが多いです。痛みの程度に波があるということは体が腹痛を治そうとしている証でもあります。
最後に
腹痛を即効で治す方法はありません。些細なことでも構いませんので、腹痛を感じる場合はお気軽に当院の消化器外来までご相談してください。平日忙しい方でも来院できるように、当院では土曜日も消化器専門外来を実施しています。
血便は何日続いていると危険ですか?
トイレで便器内をみると赤い血がポタポタと垂れていたり、お尻を拭いたティッシュに血がついているといった経験をされた方もいらっしゃるかと思います。血便がみられている際は身体からのSOSのサインでもありますので見逃してはいけませんが、「ただの痔だから大丈夫。」「血便もすぐに治まるだろう。」と、軽視してしまっていて数日間様子をみてしまっている方もいらっしゃるかと思います。
本来であれば便に血が混じることも、血が便器内に垂れていることはありませんので、血便が生じている際はお早めにお近くの消化器内科を標榜しているクリニックへ受診する必要があります。診察をしていると患者さんからよく、『血便は何日続いたら危ないですか?』という質問を受けることがありますので、今回は『血便は何日続いたら危ないですか?』について解説していきます。
そもそも血便とは?
血便とは、便に血が混じっている状態のことを言います。お腹の中で出血している場所や出血の原因によって、血の色などが異なります。
|
便の見た目 |
出血が疑われる部位 |
主な原因 |
|
真っ赤な便(鮮血便) |
肛門・直腸・S状結腸 |
痔、裂肛(切れ痔)、大腸ポリープ、直腸がん、直腸炎など |
|
暗赤色の便 |
結腸・上行結腸 |
潰瘍性大腸炎、クローン病、感染性腸炎、虚血性腸炎、大腸がん、大腸ポリープなど |
|
黒っぽくタール状の便(黒色便・タール便) |
胃・十二指腸 |
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、出血性胃炎など |
見た目だけで出血の原因を断定することは難しいです。そのため診察時では、「血便が何日続いているか?」「血便のほかに腹痛や下痢などの消化器症状も併発しているか?」などもあわせて確認をさせていただいています。
血便が生じる原因について
血便を引き起こす病気には大きく、下記のようなものがあります。
・ 痔(いぼ痔・切れ痔)
・大腸ポリープ・大腸がん
・感染性腸炎
・潰瘍性大腸炎・クローン病(炎症性腸疾患)
・虚血性腸炎
血便は何日続くと危険ですか?
血便がみられる際はお腹の中で異常が生じているSOSサインです。出血量に関わらず、お早めに消化器内科を標榜しているクリニックに受診するようにしてください。
受診の目安
痔や一時的な感染性の腸炎であれば、血便がみられていたとしても1〜2日で治まることがあります。そのため、血便が2日以上みられる際は受診するようにしてください。その際はお腹の中を詳しく確認するために大腸カメラ検査を行っているクリニックへ受診してください。
最後に
痔や感染性の腸炎で血便が生じることもありますが、血便が2日以上続いている場合はそれは『体からの異常を知らせるSOSサイン』となります。血便が2日以上続く際は必ずクリニックを受診するようにしてください。
当院では消化器外来にも力を入れており、血便の診察や検査、治療も行っています。些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。
血便がでたらどこに行けばいいの?という疑問を解説します!
トイレで便を見ると血が混じっていると誰しもが驚きと不安を感じることになるかと思います。
「もしかしてなんかの病気なのかな。。?」「もしかしたら大腸がんかもしれない。。」「値が出ているけどこのまま様子をみてていいのかな?」「何科に受診したらいいの?」などと、血便が生じた際に悩まれた経験がある方もいらっしゃるかと思います。そこで、血便が生じた際に『どこに行くべきか?』といった疑問に答えるために解説をさせていただきますので血便でお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。
血便とは?
血便とは、便に血液が混じった状態のことで、血の混じり方や出血量によって、考えられる病気が異なります。
鮮やかな赤色の血(鮮血便)が出ている場合は、比較的に肛門付近から出血している可能性が高いです。そのため、痔や裂肛(切れ痔)、直腸がんや直腸ポリープといった腫瘍、直腸の炎症などの病気が原因となることがあります。
便が暗赤色(赤黒い)場合には、大腸の奥の方(S状結腸〜横行結腸〜上行結腸・盲腸)から出血している科の性が高いです。そのため、大腸がんや大腸ポリープといった腫瘍、潰瘍性大腸炎・クローン病、感染性腸炎・虚血性腸炎などの病気が原因となることがあります。
黒っぽいタール状の便(黒色便)の場合は、食道、胃や十二指腸などの上部消化管からの出血している可能性が高いです。そのため、胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃がんなどの病気が原因となることがあります。
血便がでた際にクリニックを選ぶ際のポイントについて
血便が生じた際、または普段の便の色とは異なるなと思った際に、クリニックを受診していただければと思います。クリニックにてお越しいただいたら必要に応じて、精密検査(内視鏡検査)を受けていただくことを推奨します。
血便は「消化器内科」を標榜しているクリニックまで
血便が生じる原因の多くは、消化管(特に大腸)からの出血が関係していることが多いです。そのため、血便が生じている際はまず消化器内科を標榜しているクリニックへ受診してください。診察時は血便の原因を確認するために以下のような診察・検査を行っていきます。
・問診・診察・・・血便の性状・腹痛などの他の消化器症状の有無を確認する
・血液検査・・・炎症や貧血の有無を確認する
・内視鏡検査 (大腸カメラ検査)・・・出血原因を特定するために行う検査です。内視鏡検査でがんなどの病気が関わっていないか確認する
血便は大腸カメラ検査を
大腸カメラ検査)は、先端についているカメラで直接的に腸の粘膜を観察することができる検査です。検査時にポリープや腫瘍、炎症などの有無を確認することができます。検査時に必要があればその場で組織検査(生検)やポリープの切除も可能です。
大腸カメラ検査では出血が生じている原因を特定することができ、確定診断が可能となります。血便が生じてる際は消化器内科を標榜しており、大腸カメラ検査まで力を入れているクリニックへご相談されることを推奨します。
数ある消化器内科クリニックの中からクリニックを選ぶ際のポイント
内視鏡検査(胃カメラ検査・大腸カメラ検査)を行っているクリニックは近年増加傾向にあります。数ある消化器内科クリニックから選ぶ際のポイントについて下記に記載をいたします。ぜひ参考にしていただければと思います。
・勤務している医師は今までに何例の内視鏡検査の実績があるのか
・内視鏡検査時に鎮静剤を使用しているか
・最新の機器を導入しているか
・HP上にどれくらい内視鏡検査関連のコンテンツを取り揃えているか など
当院では、これまでに2万例以上の内視鏡検査の実績がある院長が、内視鏡検査を皆様に提供をしております。内視鏡検査時の苦痛に配慮し、快適に検査を受けていただけるように様々な工夫を行っております。内視鏡検査についてはお気軽にお相談ください。
最後に
「血便がでたらどこに行くべきか?」というお悩みを抱えている方はぜひ参考にしていただければと思います。
血便は健康であれば生じないため、血便が生じている際は体が何かしらの異常を知らせている重要なサインとなります。血便がみられた際は軽視をせず、お近くの消化器内科のクリニックまでご相談してください。
大腸がんは男女ともに患者数やがん死亡率が上位を占めています。そんな大腸がんですが、初期症状として血便があげられます。ただの痔だから大丈夫と思っていても、実は大腸がんであったというケースもあります。血便がでたらまずは消化器内科を標榜しているクリニックを受診し、必要に応じて内視鏡検査を受けるようにしてください。
心配いらない血便ってあるの?について詳しく解説します
血便とは?
便に血が混ざっている状態を血便と言います。血便が生じる原因は様々あり、食道や胃、十二指腸、大腸、直腸、肛門などの消化管で異常が生じると、出血がでてしまうことがあります。本来であれば便に血が混じることはありません。そのため、便に血が混じっている場合は早急にご相談ください。
心配いらない血便ってあるの?
血便が生じても、『直ぐに治まるから大丈夫!』『ただの痔だから大丈夫!』と言っている方もいらっしゃいますが、結論からお伝えしますと、心配のいらない血便はありません。一般的には、血便は異常が生じているサインで、決して無視してもいいものではありません。
健康診断などで実施する便潜血検査は、便中への血液の混入の有無を検査することができます。便潜血検査では目視では確認することができないくらい微量な血液の混入でも判定することができます。
仮にこの便潜血検査で陽性と指摘を受けても、排便時に目視で血液の混入が分かるくらい出血量がなければ、クリニックを受診しようと思わない方もいらっしゃるかと思います。ただ、治療をせずに放置していると余計に重症化していき出血量が増え、貧血やふらつき、頭痛、動悸、低血圧などの重大な病状へと悪化してしまう場合もあります。
普段よりも便の色がなんとなく赤っぽい、便器内に血が垂れていた、真っ黒い便が出たなどの経験がある方はお早めにご相談してください。早急に消化管中を精密検査し、出血が生じている原因を解明していく必要があります。
血便は大腸カメラ検査を
血便で受診をされた場合、問診内容からある程度どのような病気であるかは検討がつきますが、正確に診断を行うとなると大腸カメラ検査でお腹の中を詳しく観察していく必要があります。
大腸カメラ検査を行い、検査時に切除可能な大腸ポリープを見つけた場合は、その場で大腸ポリープ切除を行うことができます。切除ができないくらい大きい大腸ポリープであったら、後日お近くの病院へ紹介する場合もあります。検査時に大腸がんが疑われる部位を見つけた時には、早期の大腸がんか進行性の大腸がんなのかを観察し、必要に応じて組織検査を実施しています。血便がでた場合はお早めに大腸カメラ検査を受けるようにしてください。
最後に
大腸がんは近年、男女ともに患者数や死亡率が増加傾向にあります。初期症状を感じにくい特徴があり、早期発見が難しい大腸がんですが、血便は大腸がん発症時の初期症状の一つでもあります。そのため、血便が生じた際は決して軽視しない方が良いです。
血便が生じた際に心配はないと思っている方もいらっしゃるケースがありますが、その出血が大腸がんが原因となっている可能性もございます。大腸がんが原因となっていないかを確認するためにも一度は内視鏡検査を受けていただければと思います。
当院が大腸カメラ検査に拘るわけ
「大腸カメラは、前処置が大変そう」「検査が苦しそう」といった不安から、大腸カメラ検査をためらう方は少なくありません。しかし、私たちが大腸カメラ検査にこだわるのは、その不安を乗り越えてでも検査を受けていただく必要性を痛感しているからです。
〇1万例以上の経験が語る「早期発見」の重要性
私はこれまでに1万例以上の大腸カメラ検査を手がけてきました。その多くの経験から、大腸がんが、放置すれば命に関わる病気であると同時に、早期に発見できれば治癒率が非常に高い病気であることを痛感しています。
大腸がんは、ポリープという良性の段階から時間をかけてゆっくりと進行することが少なくありません。この段階でポリープを発見し、切除することで、将来の大腸がんを予防することができます。大腸がんで亡くなる方を一人でも多く減らしたい、究極的にはゼロにしたいという強い想いがあるからこそ、私たちは検査を最重要視しているのです。
〇最新機器と熟練の技術で「見落とさない」
当院では、最新鋭のオリンパス社製内視鏡システムEVIS X1を導入しています。この機器は、小さな病変も鮮明に映し出し、肉眼では判別が難しい病変の早期発見を可能にします。
ただし、どんなに優れた機器でも、それを使う医師の技術がなければ真価を発揮しません。大腸カメラは、腸の曲がりくねった部分を慎重に進める繊細な技術が求められます。私は、最新機器と熟練した医師の確かな技術を組み合わせることで、「見落とさない」検査を追求し、患者様の命を守ることにこだわっています。
〇検査を「嫌なこと」にしない、そして「いつでも受けられる」ように
大腸カメラ検査を「嫌だ」「怖い」と感じる方が多いからこそ、当院では患者様の負担を減らすことに細心の注意を払っています。検査前の下剤を無理なく服用していただけるよう工夫したり、鎮静剤を使って眠ったような状態で検査を受けていただけるようにしたりするのも、そのためです。
検査が苦痛だと感じてしまうと、次回の検査をためらってしまい、その間に病気が進行してしまうかもしれません。私たちは、検査を「嫌なこと」にしないことに加えて、土曜日も検査を実施したり、朝の時間を有効活用できるモーニング大腸カメラに対応したりすることで、患者様が定期的に健康チェックを受けやすい環境を整えたいと考えています。
〇検査から治療、そしてその先まで
当院は、検査をして終わりではありません。検査時に見つかったポリープはその場で切除することができます。大腸カメラ検査を通じて、患者様の現在の健康状態を正確に把握し、未来の健康を守るための最適なプランをご提案します。
便の異常や健康診断で便潜血陽性を指摘された方は、どうぞご相談ください。大腸がんの予防と早期発見のために、一歩踏み出していただくことを心よりお勧めします。
当院が胃カメラ検査に拘るわけ
「胃カメラは苦しい」というイメージは、数十年前に主流だった太い内視鏡や、鎮静剤を使わない検査経験から来ていることが多いようです。しかし、現在の胃カメラ検査は、患者様の負担が大きく軽減されています。私が胃カメラ検査にこだわるのは、単に苦痛を減らすためだけではありません。
〇1万例以上の経験が語る「早期発見」の重要性
私はこれまでに1万例以上の胃カメラ検査を手がけてきました。その多くの経験から、胃がんをはじめとする深刻な病気が、初期には自覚症状がほとんどないことを痛感しています。
早期の胃がんは、内視鏡で切除できる可能性が高く、患者様の身体的な負担や治療期間を大幅に減らすことができます。しかし、症状が出てからでは手遅れになることも少なくありません。私が胃カメラ検査にこだわるのは、胃がんで亡くなる方を一人でも多く減らしたい、究極的にはゼロにしたいという強い想いがあるからです。
〇最新機器と熟練の技術で「見落とさない」
当院では、最新鋭のオリンパス社製内視鏡システムEVIS X1を導入しています。この機器は、小さな粘膜の変化も鮮明に映し出し、肉眼では判別が難しい病変の早期発見を可能にします。
ただし、どんなに優れた機器でも、それを使う医師の技術がなければ真価を発揮しません。私は、最新機器と熟練した医師の確かな技術を組み合わせることで、「見落とさない」検査を追求し、患者様の命を守ることにこだわっています。
〇検査を「嫌なこと」にしない、そして「いつでも受けられる」ように
胃カメラ検査を「嫌だ」「怖い」と感じる方が多いからこそ、当院では患者様の負担を減らすことに細心の注意を払っています。鎮静剤を使って眠ったような状態で検査を受けていただけるようにしたり、鎮静剤を使わない場合は鼻から入れる経鼻内視鏡を選んでいただけるようにしたりするのも、そのためです。
検査が苦痛だと感じてしまうと、次回の検査をためらってしまい、その間に病気が進行してしまうかもしれません。私たちは、検査を「嫌なこと」にしないことに加えて、急な症状がある方のために当日検査に対応したり、平日お忙しい方でも受けていただけるよう土曜日も検査を実施したりすることで、患者様が定期的に健康チェックを受けやすい環境を整えたいと考えています。
〇検査から治療、そしてその先まで
当院は、検査をして終わりではありません。ピロリ菌の除菌治療や、軽度のポリープ切除まで、検査から治療まで一貫してサポートします。
私たちは、胃カメラ検査を通じて、患者様の現在の健康状態を正確に把握し、未来の健康を守るための最適なプランをご提案します。些細な胃の不調でも構いません。ご自身の胃の健康のために、一度当院にご相談ください。
胃の痛み、もしかして胃潰瘍? 専門医が解説する胃潰瘍の症状と治療
胃の痛み、もしかして胃潰瘍? 専門医が解説する胃潰瘍の症状と治療
「胃がキリキリ痛む」「食後にみぞおちが重苦しい」「なんだか胃がムカムカする」…これらの症状に心当たりはありませんか? 日常生活でよく経験する胃の不調ですが、もしかしたらそれは「胃潰瘍」かもしれません。
今回は、消化器内科の視点から、胃潰瘍とはどのような病気なのか、その症状や原因、そして治療法について詳しく解説していきます。胃の不調でお悩みの方や、胃潰瘍について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
胃潰瘍とはどんな病気?
胃潰瘍とは、胃の粘膜が深く傷つき、ただれたりえぐれたりする病気です。胃の粘膜は通常、胃酸から自身を守るための防御機能を持っていますが、何らかの原因でこの防御機能が弱まり、胃酸によって粘膜で炎症が生じてしまいます。
潰瘍が深い場合、胃壁に穴が開いてしまう「穿孔(せんこう)」という状態になることもあり、これは緊急性の高い非常に危険な状態です。また、潰瘍からの出血によって、吐血や黒い便(タール便)が出るといった症状が現れることもあります。
そして、忘れてはならないのが、胃潰瘍が進行する過程や原因菌の感染が、胃がんのリスクを高めるということです。特に慢性的な炎症は、胃がんの発生と深く関わっているため、軽視はできません。
胃潰瘍の主な原因
胃潰瘍の原因は、かつてはストレスが主な原因と考えられていましたが、最近では以下の2つが大きな割合を占めることがわかっています。
・ヘリコバクター・ピロリ菌感染
ピロリ菌は、胃の粘膜に生息する細菌で、慢性的な炎症を引き起こし、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんの原因となることが明らかになっています。日本人では、特に中高年の方に感染者が多く、感染していると潰瘍の再発リスクも高まります。
・非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の使用
風邪薬や頭痛薬として広く使われている非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、痛みを抑える効果がありますが、同時に胃の粘膜を保護するプロスタグランジンの生成を阻害することで、胃の防御機能を低下させ、潰瘍を引き起こすことがあります。
もちろん、ストレスや喫煙、過度の飲酒なども胃潰瘍の発症や悪化に関与することがあります。これらは直接の原因というよりは、胃の防御機能を弱めたり、攻撃因子を強めたりする間接的な要因として考えられています。
胃潰瘍の主な症状
胃潰瘍の症状は多岐にわたりますが、代表的なものとしては以下のような症状が挙げられます。
・胃の痛み
最も一般的な症状で、みぞおちのあたりに痛みを感じることが多いです。空腹時に痛むこともあれば、食後に痛むこともあります。キリキリとした痛みや、焼け付くような痛み、重苦しい痛みなど、感じ方は様々です。
・吐き気、嘔吐
胃の働きが悪くなることで、吐き気や嘔吐の症状が出ることがあります。
・胸焼け、胃もたれ
胃酸が逆流して胸焼けを感じたり、消化不良による胃もたれを感じたりすることもあります。
・食欲不振、体重減少
胃の不調が続くことで食欲が低下し、体重が減少することもあります。
・吐血、黒い便(タール便)
潰瘍からの出血がある場合、吐血したり、便が黒くなることがあります。これは、出血した血液が胃酸と反応して黒くなるためで、非常に危険なサインです。このような症状が見られた場合は、すぐに医療機関を受診してください。
胃潰瘍の診断と治療法
胃潰瘍の診断には、主に胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)が用いられます。胃カメラ検査では、食道、胃、十二指腸の粘膜を直接観察し、潰瘍の有無や程度を確認することができます。また、潰瘍の原因を特定するために、必要に応じて組織の一部を採取して病理検査を行ったり、ピロリ菌の検査を行うこともあります。胃潰瘍の症状の陰に胃がんが隠れている可能性もあるため、内視鏡による精密な観察は非常に重要です。胃潰瘍の治療は、原因に応じて異なります。
・薬物療法
胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬やH2ブロッカーなど)や、胃の粘膜を保護する薬などが処方されます。これらの薬を服用することで、潰瘍の治癒を促します。
・ピロリ菌の除菌治療
ピロリ菌が原因で胃潰瘍が発症している場合は、抗生物質と胃酸分泌抑制剤を併用してピロリ菌を除菌する治療が行われます。除菌に成功すれば、胃潰瘍の再発リスクを大幅に減らすことができます。
・生活習慣の改善
喫煙や過度の飲酒を控え、ストレスを溜めないようにすることも大切です。また、刺激物の多い食事や不規則な食生活も胃に負担をかけるため、見直す必要があります。
当院では、胃の不調で来院された患者様に対し、丁寧な問診と必要な検査を通じて、適切な診断と治療を心がけております。胃カメラ検査も、患者様の負担を軽減できるよう、細心の注意を払って実施しておりますのでご安心ください。
早期発見・早期治療が大切です
胃の痛みや不調は、日常的なものと軽く考えがちですが、放置すると重篤な病気につながる可能性もあります。特に、胃潰瘍は再発しやすい病気でもあります。軽症だと思っても、その陰に胃がんが潜んでいる可能性もゼロではありません。気になる症状がある場合は、自己判断せずに、ぜひ一度当院にご相談ください。早期に診断し、適切な治療を行うことで、症状の改善だけでなく、将来の合併症を防ぐことにもつながります。ご自身の胃の健康のためにも、早めの受診をお勧めいたします。
胃カメラは苦しい? 専門医が解説する胃カメラ検査の「今」
胃カメラは苦しい? 専門医が解説する胃カメラ検査の「今」
胃の痛み、胃もたれ、胸焼け…これらは多くの方が経験する、胃の不調のサインです。しかし、これらの症状が一時的なものなのか、それとも何か深刻な病気が隠れているのかを正確に知るためには、胃カメラ検査が非常に有効です。
胃カメラ、正式には上部消化管内視鏡検査と言いますが、「苦しい」「辛い」といったイメージをお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。特に、過去に検査を受けたことがある方の中には、そのような経験から、もう二度と受けたくないと感じている方もいらっしゃるかもしれません
しかし、胃カメラ検査は日々進化しており、以前に比べて格段に楽に、そして安全に受けられるようになっています。今回は、消化器内科の視点から、胃カメラ検査の重要性とその「今」について詳しく解説していきます。
胃カメラ検査がなぜ重要なのか?
胃の不調を感じた際、「市販薬で様子を見よう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、軽い胃もたれ程度であればそれで改善することもあります。しかし、症状が長引いたり、頻繁に繰り返したりする場合は、医療機関を受診し、適切な検査を受けることが非常に大切です。
胃カメラ検査では、食道、胃、十二指腸の粘膜を直接観察することができます。これにより、胃炎や胃潰瘍、ポリープ、逆流性食道炎といった良性の疾患だけでなく、早期の胃がんや食道がん、十二指腸がんといった悪性疾患の発見も可能です。特に、がんは早期発見・早期治療が非常に重要であり、胃カメラ検査はがんの早期発見に最も有効な手段の一つと言えます。
また、検査中に疑わしい病変が見つかった場合には、その場で組織の一部を採取(生検)し、病理検査に回すことも可能です。これにより、より正確な診断を下すことができます。
「苦しい」は昔の話? 最近の胃カメラ検査について
「胃カメラは苦しい」というイメージは、鎮静剤を使用しない検査経験や主に数十年前に主流だった太い内視鏡から来ていることが多いようです。しかし、現在の胃カメラ検査は、医療技術の進歩により、患者様の負担が大きく軽減されています。
鎮静剤
まず、鎮静剤の使用があります。眠ったような状態で検査を受けていただけるよう、ご希望に応じて鎮静剤を使用することが可能です。鎮静剤を使用することで、検査中の不快感や不安を大幅に軽減し、よりリラックスした状態で検査を受けていただけます。ウトウトしている間に検査が終わっていた、という方も少なくありません。
経鼻内視鏡
もう一点は、内視鏡の細径化です。当院で導入している内視鏡も、非常に細いタイプで、鼻から挿入する経鼻内視鏡検査が選択肢の一つとなっています。経鼻内視鏡は、舌の付け根に内視鏡スコープが触れないため、吐き気を催しにくいというメリットがあります。会話も可能なため、検査中に医師とコミュニケーションを取りながら進めることもできます。
※当院では、経鼻内視鏡と鎮静剤を併用することはありません。
患者様の状態やご希望に合わせて、どちらか一方の方法で検査を実施いたします。これにより、それぞれの方法のメリットを最大限に活かし、より安全で快適な検査を受けていただけます。
さらに、医師の技術も検査の快適さに大きく影響します。患者様の状態を細やかに観察し、声かけをしながら、できるだけ負担の少ないように検査を進めます。当院では、胃カメラ検査の経験が豊富な消化器内科医が担当いたしますので、どうぞご安心ください。
胃カメラ検査を検討されている方へ
胃の不調は、日々の生活の質を低下させるだけでなく、放置すると重大な病気につながる可能性もあります。少しでも気になる症状があれば、ぜひ一度、消化器内科を受診し、ご相談ください。
当院では、患者様一人ひとりの状態やご希望に合わせて、最適な検査方法をご提案いたします。胃カメラ検査に対する不安や疑問があれば、遠慮なくお申し出ください。検査前に丁寧にご説明し、納得いただいた上で検査を受けていただけるよう努めております。
胃カメラ検査は、ご自身の胃の健康状態を知る上で非常に大切な検査です。定期的な検査を受けることで、病気の早期発見・早期治療につながり、安心して毎日を過ごすことができます。ぜひこの機会に、ご自身の胃と向き合ってみませんか。
大腸カメラ検査後の食事:あなたの胃腸をいたわるやさしい選択
大腸カメラ検査後は、食事制限や下剤服用で、お腹が空いていることと思います。しかし、検査後の食事は、ただ空腹を満たすだけでなく、デリケートになった胃腸をいたわる大切なプロセスです。消化器内科の観点から、検査後の適切な食事について詳しくご紹介します。
検査後の胃腸の状態を理解する
大腸カメラ検査では、腸の中をきれいにするために下剤を服用し、検査中は空気を入れて腸を膨らませます。これにより、普段以上に腸が刺激され、デリケートな状態になっています。
このデリケートな状態の時に、いきなり刺激の強いものや消化に悪いものを摂ると、腹痛や下痢、お腹の張りなどの不調を引き起こしたり、ポリープ切除後の場合は出血のリスクを高めたりする可能性があります。
食事再開のタイミングと最初の食事
検査終了後、鎮静剤を使用した場合でも、通常1時間から1時間半程度で効果が切れてきます。まずは少量の水をゆっくりと飲み、むせたり気分が悪くなったりしないか確認しましょう。問題がなければ、その後から食事を始めていただいて構いません。
最初の食事は、胃腸に負担をかけない消化の良いものを選び、腹八分目にとどめることが大切です。
具体的には、以下のようなものがおすすめです。
- 主食: 白がゆ、具なしの素うどん、よく煮込んだ雑炊、食パン(耳なし)
- たんぱく質: 豆腐、はんぺん、白身魚(煮る・蒸すなど調理法に注意)、鶏のささみ(よく煮込んだもの)
その他、半熟卵、茶碗蒸し、ゼリー等もおすすめです。
避けるべき食品と注意点
検査後の胃腸を刺激しないために、以下の食品はしばらく避けるようにしましょう。特に、ポリープを切除した場合は、1週間程度は注意が必要です。
- 消化に悪いもの:
- 食物繊維の多いもの(ごぼう、レンコン、きのこ類、海藻類、玄米、全粒粉パンなど)
- 脂質の多いもの(揚げ物、炒め物、脂肪の多い肉、加工肉、バター、マヨネーズなど)
- ナッツ類、種子の多い果物(キウイ、イチゴ、柑橘類など)
- 刺激物:
- 辛いもの(唐辛子、キムチ、香辛料を多く使った料理など)
- 酸味の強いもの(レモン、お酢など)
- 炭酸飲料、アルコール、コーヒー、紅茶(カフェインを多く含むもの)
アルコールは血行を促進し、出血のリスクを高める可能性があるため、特にポリープ切除後は数日間は控えるようにしてください。喫煙も腸に負担をかけるため、同様に控えることをおすすめします。
ポリープ切除後の特別な注意点
大腸ポリープを切除した場合は、切除部位の粘膜が完全に回復するまでに時間がかかります。術後の出血や穿孔(腸に穴が開くこと)などの合併症を防ぐためにも、医師の指示を厳守することが非常に重要です。
通常、1週間程度は消化の良い食事を心がけ、激しい運動や長時間の移動、飲酒、刺激物の摂取は控えます。具体的な期間や注意点は、切除したポリープの大きさや数、患者様の状態によって異なりますので、必ず医師からの説明をよく聞いてください。
日常生活への移行
検査後、何も処置がなかった場合は、翌日からは基本的に普段通りの食事に戻しても問題ありません。しかし、胃腸が空っぽの状態から一気に普段の食事に戻すと負担がかかることもあります。数日間は消化に良いものを中心にし、徐々に通常食に戻していくのが理想的です。
当クリニックでは、大腸カメラ検査後の食事に関して、患者様一人ひとりの状態に合わせて丁寧にご説明いたします。ご不明な点や不安なことがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。皆様が安心して検査を受け、スムーズに日常生活に戻れるよう、きめ細やかなサポートを提供してまいります。
疲労回復の救世主?にんにく注射と消化器内科の意外な関係
「最近、疲れが取れない」「どこに相談したらいいかわからない」と感じていませんか?そんな時、にんにく注射という言葉を耳にすることもあるかもしれません。疲労回復に効果的と注目を集めていますが、実は消化器内科との関連も深く、身体の内側から元気を取り戻す選択肢となる可能性があります。
にんにく注射とは?その効果とメリット
にんにく注射は、にんにくそのものを注射するのではなく、主要成分であるビタミンB1誘導体(アリナミン)などを血管に直接投与する治療法です。ビタミンB1は、疲労回復に不可欠なエネルギー産生を助ける働きがあります。不足すると疲労物質が溜まり、だるさや倦怠感につながります。
にんにく注射によりビタミンB1誘導体を効率よく取り込むことで、エネルギー産生を促進し、疲労物質の蓄積を抑えることが期待できます。即効性があり、注射後すぐに体が軽くなったと感じる方も少なくありません。二日酔いの改善や肩こり、腰痛の緩和にも効果が期待でき、短時間で手軽に受けられる点もメリットです。
消化器内科と疲労回復の関係
なぜ消化器内科が疲労回復に関わるのか?それは、消化器内科が全身の健康と密接に関わっているからです。私たちは食事から栄養を吸収し、エネルギーを生み出しています。この消化吸収を担うのが胃や腸などの消化器です。
胃腸の調子が悪いと、栄養が十分に吸収されず、エネルギー不足で疲れやすくなります。また、腸内環境の悪化は免疫力低下や精神的な不調にもつながり、全身のだるさを引き起こすことがあります。
当クリニックでは、消化器系の疾患治療を通じて、栄養吸収をスムーズにし、身体が本来持つエネルギーを生み出す力を回復させることで疲労回復をサポートします。疲労の原因が消化器系の問題に起因している可能性も考慮し、にんにく注射だけでなく、消化器専門医としての視点からアドバイスや治療も提供可能です。
こんなお悩みはありませんか?
- 毎日忙しく、慢性的な疲労感が抜けない
- 寝ても疲れが取れない
- 肩こりや腰痛がひどい
- 風邪をひきやすい、免疫力が落ちた気がする
- ストレスが多く、体調を崩しやすい
- 二日酔いを早く治したい
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度当クリニックにご相談ください。にんにく注射は、一時的な疲労回復だけでなく、体の内側から健康をサポートする一歩となるかもしれません。
にんにく注射を受ける際の注意点
にんにく注射は比較的安全ですが、すべての方に適しているわけではありません。妊娠中の方、授乳中の方、アレルギーをお持ちの方、基礎疾患をお持ちの方などは、事前に医師にご相談ください。当クリニックでは、患者様一人ひとりの健康状態をしっかりと把握し、安心して治療を受けていただけるよう丁寧なカウンセリングを行います。
まとめ
にんにく注射は、即効性のある疲労回復効果が期待できる治療法です。消化器内科が全身の健康と密接に関わっていることを考えると、単なる対症療法としてだけでなく、身体の根本的な調子を整える選択肢としても有効です。
当クリニックでは、皆様が毎日を元気に過ごせるよう、にんにく注射を含めた様々なアプローチでサポートさせていただきます。お体の不調や疲労感でお悩みの方は、ぜひお気軽にご来院ください。一緒に、心身ともに健康な状態を目指しましょう。
腸内フローラ検査は保険適応になりますか? ―腸内フローラ検査について内科医が解説します―
最近、テレビや雑誌などでもよく耳にするようになった「腸内フローラ」。
腸内には約100兆個以上の腸内細菌が存在しており、その種類やバランスは人それぞれで異なります。これらの腸内細菌叢が、みなさんの健康や病気に深く関わっていることが報告されています。そして、その腸内環境を調べるための検査が、「腸内フローラ検査」です。
今回は、そもそも腸内フローラとは何か、検査では何がわかるのか、検査費用や保険適用の有無、どんな方に腸内フローラ検査はおすすめなのかなどを解説いたします。
腸内フローラとは?
腸内フローラとは、腸内に生息する細菌の集団のことを指します。顕微鏡で見ると、まるでお花畑(flora)のように見えることから、「腸内フローラ」と言われています。主に以下のような細菌が腸内に生息しています。
善玉菌(例:ビフィズス菌、乳酸菌など):腸内環境を整え、免疫力を高めてくれる
悪玉菌(例:ウェルシュ菌、大腸菌など):腐敗物質を産生し、腸の不調を引き起こす
日和見菌:善玉・悪玉の優劣に応じて働き方が変わる細菌
腸内細菌のバランスが良い(善玉菌が多い)と便通が整い、免疫機能や代謝、精神的な安定などにも良い影響があります。 逆に腸内細菌のバランスが崩れる(悪玉菌が多い)と、便秘・下痢・アレルギー・肥満・うつ病・糖尿病・大腸がんなどのリスクが高まるとも言われています。
腸内フローラ検査とは?
腸内フローラ検査とは便を採取し、腸内細菌の構成を詳しく調べる検査です。ただ便を採取するだけとなりますので非常に簡単に検査が受けられます。
【腸内フローラ検査でわかること】
・善玉菌・悪玉菌・日和見菌の割合
・ビフィズス菌や乳酸菌の有無・量
・肥満型フローラ・やせ型フローラの傾向
・炎症リスクや腸内のバランス
・腸内年齢の推定
腸内フローラ検査を受けることで「腸内細菌のバランスが良いのか?」「体質的にどんな病気に注意すべきか?」などを知ることができます。
腸内フローラ検査は保険適応になるのか?
ここで多くの方が気になるのが、「腸内フローラ検査は保険適応になるのか?」という点です。よくお越しいただく患者さんからも質問をうけます。結論から申しますと、現時点では、腸内フローラ検査は保険診療の適応外となってしまいます。つまり、健康保険証を使った3割負担などでは検査が受けられず、自費診療(自由診療)となってしまいます。
【なぜ保険がきかないのか?】
腸内フローラ検査は病気の診断や治療のためではなく、『体質の傾向を知るための“予防医学的検査”』として実施されています。腸内フローラ検査では「リスク傾向」や「腸内のタイプ」を把握することにとどまるため、保険診療の適応とはなりません。
どんな方に腸内フローラ検査がおすすめ?
腸内フローラ検査は、以下のような方にとって特に有用です。
・慢性的に便秘や下痢が続いている
・お腹が張りやすい
・食生活が乱れている(偏食である)
・疲れやすい、風邪をひきやすい
・花粉症やアトピーなどのアレルギー体質である
・痩せにくい、痩せてもすぐにリバウンドする
・肌荒れ、ニキビが気になる
・サプリメントや腸活の効果を見極めたい
上記のようなお悩みを抱えている方には腸内フローラ検査は有用であります。
腸内フローラ検査の流れ
腸内フローラ検査の流れは非常にシンプルです。以下のような手順となります。
- キットの購入・配布(医療機関または郵送)
- 自宅で便を採取(専用スティックで少量を採取)
- 検査機関に提出(郵送)
- 数週間後に結果レポートがクリニックに届く
- 医師や管理栄養士がフィードバック
腸内フローラ検査の結果をどう活かすのか?
腸内フローラ検査の結果は、あくまで“現時点での腸内環境の状態”を示します。そのため、「悪いからすぐ病気になる」ということではありませんのでご安心ください。
大切なのは、結果をもとに今後の生活習慣を見直し、腸内環境を改善させることです。
たとえば腸内フローラ検査の結果をみて
・食物繊維を意識的に摂取する(野菜・海藻・発酵食品)
・ビフィズス菌や乳酸菌入りのヨーグルトを取り入れる
・自身にあった睡眠時間を意識する
・ストレスケアに気をつける
管理栄養士が検査結果に応じて栄養指導を実施
当院には食事のプロである管理栄養士が複数名在籍しています。食事に不安のある方に対して、管理栄養士が栄養指導を実施して、健康増進をサポートしています。
栄養指導の際には患者さんごとにカスタマイズし、ご体調に応じて食事や運動に関しても指導しています。普段家事をされない方にはスーパーでのお惣菜の選び方や外食時のポイントなどもお伝えしています。栄養指導をご希望の方はお気軽にご相談ください。
腸内フローラ検査は“未来の健康”への投資
腸内環境は、単なるお腹の調子だけでなく、免疫・代謝・メンタル・病気のリスクなど、多方面に関わっています。 腸内フローラ検査はその状態を可視化し、自分の体質に合わせた食事や生活習慣を見直すためのヒントとなります。
この腸内フローラ検査は自費診療となります。 費用や目的を考えたうえで、「自分の腸の状態を知っておきたい」「より健康に過ごしたい」という方には、十分に価値のある検査といえます。健康は腸から。あなたの“腸の声”に、一度耳を傾けてみませんか?
排便後に腹痛を感じるのはなぜ? ―見逃してはいけない腹痛の原因と対処法を内科医が解説―
腹痛は誰もが経験したことのある症状かと思います。腹痛が生じるタイミングは食後、空腹時、ストレス時などさまざまですが、中には「排便後に腹痛を感じる」という方は意外に多くいらっしゃいます。
排便とは、腸内にたまった不要な物を体外に出す行為であり、排便後にはスッキリするはずですが、排便後に腹痛を感じたり、逆に痛みが強くなったりする場合は、腸の働きやお腹の病気が関係している可能性があります。本日は便通後の腹痛の原因や対処法、そして受診の目安について解説していきます。
排便後の腹痛、よくある原因について
① 過敏性腸症候群(IBS)
排便後に腹痛を感じる最も代表的な原因のひとつが過敏性腸症候群(IBS:Irritable Bowel Syndrome)といわれる病気です。
これは腸管に明らかな炎症や潰瘍がないにも関わらず、便通異常(下痢や便秘、またはその両方)や腹痛、お腹の張りなどの症状が続きます。
IBSは自律神経や腸内環境のバランスが崩れることで発症すると言われており、20〜40代の若年層に多く見られます。命に関わる病気ではありませんが、便通異常が慢性的に続くことで生活の質(QOL)を大きく下げる原因になります。
② 痔や肛門周囲の疾患
排便後に肛門のあたりがズキズキと痛む場合や、下腹部にも痛みが広がっている場合、痔(特に裂肛・切れ痔)や肛門周囲膿瘍などの可能性があります。硬い便が出る際に肛門が裂けて出血してしまう場合や、便が出た後しばらくしてから鈍い痛みが残る場合は要注意してください。
③ 便秘・硬便
便秘で便が腸内に長くとどまってしまうと水分が吸収されて便が硬くなり、排便時に腸が強く刺激されます。このとき、腸管の便を体外出そうとする蠕動運動(ぜんどううんどう)が強まり、排便後に痛みが残ることがあります。
特に、排便してもすっきりしない「残便感」や、下腹部の鈍痛を伴う場合は、便秘型IBSや機能性便秘の可能性も考えられます。
④ 腸管のけいれん
ストレスや身体の冷えなどによって、腸の動きが過剰になってしまうと、腸けいれんが起こることがあります。これは腸の筋肉が急に収縮することで、排便後にキリキリ・チクチクとした痛みを感じることがあります。けいれん性の痛みは、波のように繰り返し襲ってくるのが特徴となります。
⑤ 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
便に血が混じっていたり、長期間にわたって排便後の痛みが続いたりする場合は、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患の可能性も考えられま。これらは国が指定する難病の一種であり、若年者に多く、早期診断・治療が重要となります。
「排便後の腹痛」は身体からのSOSのサイン
排便後の腹痛が1回限りで、すぐに腹痛が治まる場合は心配ないこともありますが、
・同じような腹痛が続いている
・便の状態がいつもと違う(細い、血が混じってるなど)
・排便のたびに強い痛みを感じる
・下痢と便秘を繰り返している
こうした症状がある場合は、「ただの体調不良」や「ストレスのせい」だけでは済まないかもしれません。お早めにご相談ください。
痛みを和らげるためのライフケア
① 食事内容の見直し
・食物繊維を豊富に含む食品を摂る(便秘・硬便の改善)
・香辛料や脂っこいものを控える(腸の刺激を避ける)
・乳製品やグルテンに注意(過敏な方は腸が過剰に反応します)
② 規則正しい生活とストレス対策
・睡眠不足やストレスは腸の動きを不安定にしてしまいます
・リラックスできる趣味を作ることがIBSなどの症状改善に役立ちます
③ 水分補給と運動
・便の水分量を保つために水分摂取量は1日1.5~2Lが目安に。
・ウォーキングなど軽い運動で腸の動きを整えましょう。
④ 整腸剤や市販薬の使用
一時的に症状が生じている場合は整腸剤や便秘薬なども有効となる場合もありますが、慢性化している場合はお早めに医師の診断を受けるようにしてください。
排便後の腹痛に関するまとめ
|
原因 |
特徴 |
|
過敏性腸症候群(IBS) |
排便で痛み軽減も、繰り返す痛み。ストレス関与。 |
|
痔・肛門疾患 |
排便時・直後の肛門周囲の鋭い痛み、出血あり。 |
|
便秘・硬便 |
残便感や下腹部の鈍痛。便が硬い、出にくい。 |
|
腸けいれん |
排便後にキリキリとした波のある痛み。 |
|
炎症性腸疾患 |
下痢・血便・体重減少などを伴う慢性疾患。 |
腹痛を感じる際の受診の目安について
以下のような場合は、早めに消化器内科を標榜しているクリニックに受診されることを推奨します。
・腹痛が1週間以上続いている
・排便のたびに痛みを感じる
・血便がある(便に血がついてる)
・発熱や体重減少を伴う
さいごに
「排便後に腹痛を感じるのはなぜ?」という質問をよく受けることがありますが、排便後の腹痛には、さまざまな腸の不調や疾患が潜んでいる可能性があります。軽症で自然と症状が改善していくこともありますが、症状が繰り返される場合、症状が長引く場合は、医療機関での検査・診断が大切です。
腸は『第二の脳』とも呼ばれるほど、心身のバランスに影響を受けやすい臓器となります。腸からのサインを見逃さず、適切なケアと症状が長引く際はお早めにクリニックへ受診するようにしてください。
「白い」は健康の証!消化器と「白玉点滴」の意外な関係
近年、美容や健康に関心の高い方々の間で、「白玉点滴」という言葉を耳にすることが増えました。肌のトーンアップや疲労回復に効果があるとされ、多くの方に注目されています。しかし、この「白玉点滴」が、実は私たちの体の要である「消化器」と深く関わっていることをご存知でしょうか?
白玉点滴の主成分は「グルタチオン」と呼ばれる物質です。グルタチオンは、私たちの体内で自然に生成される抗酸化物質で、肝臓をはじめとする様々な臓器に存在しています。体内の活性酸素を除去し、細胞のダメージを防ぐことで、私たちの体をサビつきから守る、非常に重要な役割を担っています。
特に、肝臓は消化吸収された栄養素の代謝や解毒を行う、まさに体の「化学工場」ともいえる臓器です。アルコールや薬剤、添加物など、私たちが日々体内に取り入れる様々な有害物質を無毒化する役割を担っており、その過程で大量の活性酸素が発生します。グルタチオンは、この肝臓の働きをサポートし、解毒作用を高めることで、肝臓への負担を軽減します。
では、消化器内科である私たちがなぜ白玉点滴に注目するのでしょうか。それは、消化器の健康が全身の健康、ひいては美容や若々しさにも直結しているからです。例えば、肌のくすみやシミ、疲労感、だるさといった症状は、一見すると消化器とは無関係に思えるかもしれません。しかし、これらは肝臓の機能低下や腸内環境の悪化が引き起こしているケースが少なくありません。肝臓の機能が低下すると、体内の有害物質が適切に排出されず、それが肌荒れや全身のだるさとして現れることがあります。また、腸内環境が悪化すると、栄養素の吸収効率が下がり、免疫力の低下にもつながりまする可能性があります。
白玉点滴によってグルタチオンを体内に補給することは、肝臓の解毒作用を助け、細胞の酸化ストレスを軽減することに直結します。これにより、肝機能の改善が期待でき、その結果として、肌の調子が整ったり、疲労感が軽減されたりする可能性があります。美容効果が注目されがちですが、その根底には、体内の解毒能力の向上と細胞レベルでの健康維持という、非常に医学的なアプローチがあるのです。
また、私たちは日々の食事からグルタチオンを摂取することも可能です。ほうれん草、アボカド、アスパラガス、ブロッコリーなどの野菜や、ナッツ類、肉類、魚介類にもグルタチオンは含まれています。しかし、食事から摂取したグルタチオンは消化の過程で一部が分解されてしまうため、効率的に体内に取り入れるためには点滴による直接的な補給も有効な選択肢となります。
当院では、患者様の全身の健康をサポートすることを目的としています。消化器の専門家として、皆様の体の内側から輝く健康を追求するお手伝いをしたいと考えております。もし、慢性的な疲労感や肌の不調、あるいは「もっと元気になりたい」といったお悩みをお持ちでしたら、一度ご相談ください。白玉点滴が皆様の健康と美容の維持にどのように役立つか、そして皆様の消化器の健康状態も含めて、総合的な観点からアドバイスさせていただきます。体の中から「白く」輝く健康を目指し、充実した日々を送りませんか。
大腸カメラ前の食事で検査の成否が決まる!知っておきたい「準備食」の秘訣
「大腸カメラ」と聞くと、「検査が辛そう」「前処置が大変そう」といったイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、大腸カメラ検査は、大腸がんの早期発見やポリープの切除など、私たちの命を守るために非常に重要な検査です。そして、その検査の精度を高めるための鍵を握るのが、「検査前の食事」なのです。
消化器内科である私たちにとって、大腸カメラ検査は日常的に行われる検査の一つです。検査の目的は、大腸の粘膜を詳細に観察し、病変がないかを確認することです。そのためには、大腸の中をきれいに空っぽにする必要があります。もし便が残っていると、医師が病変を見落としてしまったり、最悪の場合、検査自体が中止になったりすることもあります。
大腸カメラ検査の数日前から、消化の良い食事に切り替えていただく「準備食」の期間を設けます。これは、大腸に残る便の量を減らし、検査当日の下剤の服用量を減らすことにも繋がります。一般的には、検査の3日前くらいから、食物繊維の少ない食事を心がけていただきます。
具体的にどういった食材を食べたらいいの?
具体的にどのような食材が良いのかというと、まず避けたいのは、食物繊維が豊富なもの、消化に時間のかかるものです。例えば、きのこ類、海藻類、こんにゃく、ごぼう、れんこんなどの根菜類、果物では種のあるもの(キウイ、いちごなど)や皮のあるもの(りんごの皮など)は控えてください。また、脂質の多い肉類や揚げ物、ナッツ類、牛乳や乳製品も腸に残ってしまいやすいため、避けるのが賢明です。
それでは、何を食べるべきかというと、白米やおかゆ、うどん、食パン(耳なし)、鶏むね肉(皮なし)、白身魚、卵、豆腐などが挙げられます。味付けは薄めにし、油を控えめに調理することが大切です。野菜を摂りたい場合は、繊維の少ないじゃがいもやかぶなどを柔らかく煮て食べるのが良いでしょう。飲み物に関しては、水やお茶は問題ありませんが、牛乳や果肉入りのジュースは避けてください。
検査前日には、さらに食事を制限していただきます。一般的には、検査前日の昼食までは上記のような消化の良いものを少量摂り、夕食は消化の良いおもゆや具なしの味噌汁、透明なスープなどにしていただくことが多いです。夜9時以降は、水以外の飲食は控えていただきます。
お問い合わせ
当院では、患者様が安心して検査を受けていただけるよう、検査前の食事に関する詳細な説明と、具体的な献立例をまとめた資料をお渡ししております。また、ご不明な点があれば、いつでもご質問いただけるよう、スタッフが丁寧に対応させていただきます。
「たかが食事」と思われるかもしれませんが、この検査前の食事が、大腸カメラ検査の観察精度を高めることに大きく繋がります。準備食をきちんと守っていただくことで、検査当日の下剤の服用もスムーズになり、より快適に検査を受けていただくことができます。
大腸カメラは、自覚症状がなくても定期的に受けることが推奨される検査です。特に、40歳を過ぎたら一度は検討していただきたい検査です。もし、大腸カメラ検査にご不安な点があれば、どうぞお気軽に当院にご相談ください。皆様の健康を第一に考え、安心して検査を受けていただけるよう、全力でサポートさせていただきます。適切な準備と検査で、安心の毎日を送りましょう。
ビタミンDと大腸がんについて
本日はビタミンDと大腸がんの関係性というテーマでコラムを配信させていただきます。
つい先日、ビタミンDを摂取していると消化器癌による死亡リスクが減少することの報告がありました。そのため、ここ最近になってビタミンDに関する関心が高まってきています。
ビタミンDは太陽の光を浴びることで体内で合成されます。ビタミンDの効果ですが、主に以下の2つがあげられます。
・骨を作るのに大切なカルシウムの吸収を促進
・骨の成長を促す
つまり、ビタミンDは骨の成長に関係しているため、骨粗鬆症の予防に効果が期待されています。
ただ、最近になってビタミンDには上記以外の効果があると言われています。
それが、免疫力アップ効果です。
・風邪やインフルエンザ等の感染症の予防
・大腸がんなどの消化器癌の予防
ビタミンDには上記のような効果もあり、ビタミンDのもつ免疫力アップ効果がここ最近になって注目を浴びるようになってきています。
血液中にあるビタミンDの濃度は、健康診断などでは測定されることはないため、ご自身のビタミンD値の状況や、ビタミンD値の適正数値について把握していない方が多いかと思います。
血液中のビタミンD値は『 30ng / ml 』以上あれば特に問題はないとのことで、30ng / mlを下回る場合はビタミンDが不足していることになります。
ビタミンDは体内で生成される物質ですが、食事からもビタミンDは摂取することができます。ただし、ビタミンDを豊富に含む食品は限られています。下記の食品はビタミンDを豊富に含んでいる食品の代表例です。
・いわし ・鮭 ・キノコ類 ・牡蠣 ・うなぎ ・卵 ・いくら(魚卵)
上記のような食品には、ビタミンDが豊富に含まれていますが、ただ実際のところ、食事だけでは十分な量のビタミンDを摂取することは難しいかと思います。最近ではドラッグストアでもビタミンDのサプリメント販売もされていますが、ドラッグストアなどで売られているサプリメントでは、1錠に含まれるビタミンDの配合量が少ないことが多いです。
医療機関でしか購入することができないサプリメントだと、ビタミンDが多く配合されていますので、サプリメントでのビタミンDの摂取をされる方は医療機関が販売しているサプリメントを選んでいただいた方がより効果を感じて頂けるかと思います。
当院では、医療機関でしか購入ができないMSS社のサプリメントを用意しています。また、管理栄養士による栄養指導にも当院は力をいれていますので、食事指導とサプリメント等のアドバイスも食事のプロである管理栄養士が行っています。サプリメントや食事指導にご興味のある方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
保土ヶ谷地域の医療関係者とのインタビューコンテンツを設置いたしました。vol1.薬局編
この度、保土ヶ谷地域で医療に携わる方々とのインタビューの連載を行うことになりました。
第一弾 月見台調剤薬局様 ココカラファイン保土ヶ谷店様
こちらからご覧ください。
今後も保土ヶ谷地域の医療従事者の方々との連携を深め、地域医療に貢献できればと考えております。
どうか楽しみにしていただければ幸いです。
保土ヶ谷あだちクリニック 院長
管理栄養士による栄養指導セミナーを実施します。
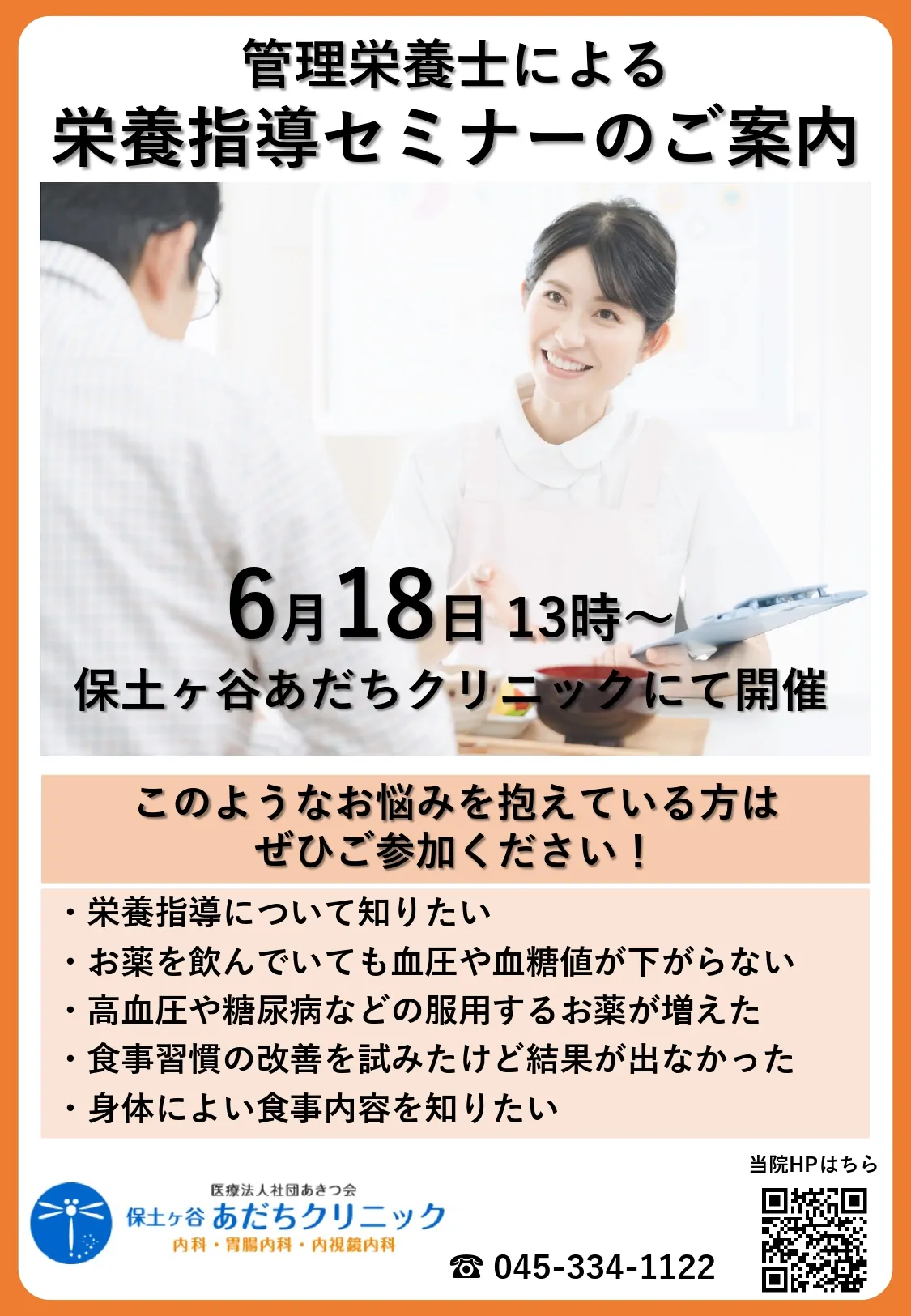
新型コロナウィルスの院内対策として 最新情報
当クリニックでは新型コロナウイルス感染症の対策としまして、患者様が安心して受診していただけますよう、3密(密閉、密集、密接)を回避し環境を整備し職員の体調管理を徹底しながら飛沫拡大防止対策として待合室の各椅子にも対策を行っております。
また、診察室はもちろん、内視鏡室をはじめ処置室などは一定期的な換気を十分に行っています。
そのほか、待合室、診察室、処置室に光触媒搭載の空気清浄器を設置し、院内感染防止を図っています。


コラムをはじめます。
宜しくお願いいたします。